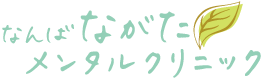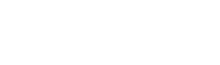注意欠如・多動性障害(ADHD)
児童精神科外来では、6歳以上15歳以下(中学3年生まで)のお子さんを対象として、子どものこころの問題を専門的に診療しています。自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害といった「発達障害」はこの年代でよく診断され、多くの事例では、健やかな発達のために特別な配慮が必要です。また、米国の診断基準では、子どもと大人は同じ基準に基づいて、うつ病、不安障害、身体表現性障害など、大人と同じ病気が診断されますが、同じ病名であっても、適切な治療はかなり異なったものです。
注意欠如・多動性障害
注意欠如・多動性障害 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) は、児童精神医学領域で最もよく研究されてきた障害の一つで、乳幼児期から児童期に発症して慢性に経過します。数多くの研究がなされていますが、生物学的な原因はまだ特定されていません。米国精神医学会の診断基準は2013年に改訂され、DSM-5となりましたが、ADHDは、神経発達障害に分類されています。
※当院では、成人期ADHDの診療は行っていません。
歴史・概念・定義
慢性の多動を呈する小児、すなわち、多動児 (hyperactive child) の存在は20世紀初頭から観察されておりましたが、中枢刺激薬が多動を軽減することが発見されたことが、今日のADHD概念が形作られていく端緒となりました(Conrad and Schneider,1992)。多動児の研究は北米で特に活発です。その流れのなか、米国精神医学会の診断基準では1980年改訂のDSM-IIIにおいて、注意欠如障害 Attention Deficit Disorder という診断カテゴリーが採用され、その後、1987年のDSM-IIIRを経て、1994年のDSM-IVでADHDという診断名が採用されました。当院では、DSM-IVに基づいてADHDを診断しています。
疫学
日本人におけるADHDの有病率は、就学前児童で31.1%(Soma et al.,2009)、8歳児の10.5%(Sugawara et al.,1999)、大学生の6.27%(Davis et al.,2012)と報告されています。就学前ADHDのかなりの割合は寛解することが知られており、当院では、6歳以上を児童精神科外来の対象としています。
臨床症状・経過
表にADHDのDSM-IV基準を示しております。ADHDで障害されているのは主として注意や衝動性を統制する機能です。典型的には、患者さんは注意がそれやすく、忘れっぽく、整理整頓やスケジュール管理が苦手です。加齢に伴って症状はある程度改善しますが、成長後にも不注意症状が残存すると、対人関係、学業、就労に影響を生じることもあります。
ADHDを伴う臨床例は、診断基準に含まれている不注意、多動性-衝動性に留まらず、易怒性、抑うつ、不安といった気分症状を伴うことが多く、反抗性や非行といった行動面の問題もよく認められます。児童期ADHDを対象とした研究では、多くの文化圏で、破壊的行動障害、不安障害、気分障害、学習障害、チック障害、遺尿症等の併存が報告されております(Brown et al.,2009;鈴木,2008)。大阪市立大学の児童精神科外来を受診した7歳から14歳のADHD41例を対象にした研究では、37%に反抗挑戦性障害が、22%に素行障害が認められました(Takahashi et al.,2007)。児童虐待や母親の精神障害は、反抗挑戦性障害や素行障害のリスクを著明に高めることが知られています(Bandou et al.,2010)。成人期ADHDでは、摂食障害、物質使用障害、パーソナリティ障害等の併存が報告されています(Brown et al.,2009)。
ADHDのDSM-IV基準
A. (1)か(2)のどちらか:
(1) 以下の不注意の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6ヵ月間持続したことがあり、その程度は不適応的で、発達の水準に相応しないもの:
(a) 学業,仕事,またはその他の活動において,しばしば綿密に注意することができない,または不注意な間違いをする。
(b) 課題または遊びの活動で注意を集中し続けることがしばしば困難である。
(c) 直接話しかけられたときにしばしば聞いていないように見える。
(d) しばしば指示に従えず,学業,用事または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)。
(e) 課題や活動を順序立てることがしばしば困難である。
(f) (学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。
(g) 課題や活動に必要なもの(例:おもちゃ,学校の宿題,鉛筆,本,または道具)をしばしばなくしてしまう。
(h) しばしば外からの刺激によってすぐ気が散ってしまう。
(i) しばしば日々の活動で忘れっぽい。
(2) 以下の不注意の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6ヵ月間持続したことがあり、その程度は不適応的で、発達の水準に相応しないもの:
(a) しばしば手足をそわそわと動かし,またはいすの上でもじもじする。
(b) しばしば教室や,その他,座っていることを要求される状況で席を離れる。
(c) しばしば,不適切な状況で,余計に走り回ったり高い所へ上がったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。
(d) しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
(e) しばしば“じっとしていない”、またはまるで“エンジンで動かされているように”行動する。
(f) しばしばしゃべりすぎる。
(g) しばしば質問が終わる前に出し抜けに答え始めてしまう。
(h) しばしば順番を待つことが困難である。
(i) しばしば他人を妨害し,邪魔する(例:会話やゲームに干渉する)。
B.多動性-衝動性または不注意の症状のいくつが7歳以前に存在し、障害を引き起こしている。
C.これらの症状による障害が2つ以上の状況において存在する。
D.社会的、学業的、または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在するという明確な証拠が存在しなければならない。
E.その症状は広汎性発達障害、統合失調症または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患(例:気分障害,不安障害,解離性障害,またはパーソナリティ障害)ではうまく説明されない。
診断・鑑別診断
不注意や衝動性は非特異的な精神症状であり、さまざまな精神障害で認められます。また、前述したように、さまざまな精神障害とADHDが併存することにも注意が必要です。DSM-5では、ADHDの鑑別診断として、反抗挑戦性障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害、反応性愛着障害、不安障害、うつ病、双極性障害、精神病性障害、パーソナリティ障害、物質使用障害、薬物の影響等が挙げられています。
児童期や青年期におけるADHDの診断は、定型的な精神発達に関する十分な知識を有した評価者が行うことが原則です。当院では、ADHDについてより信頼性の高い診断を行うことを重視しており、採血を含む身体的評価、構造化面接であるK-SADS-PL、知能検査であるWISC-IVを用いて、DSM-IV基準に基づいた診断を行っています。
治療
ADHDの医学的な治療について、患者の年代別に簡単に説明します。
1. 就学前ADHD
行動療法が第一選択となります。本邦では、6歳に満たない幼児へのコンサータやストラテラの投与は認められておらず、当院でも行っていません。
2. 児童期ADHD
ADHDを伴う6歳以上の児童では、行動療法に加えて、コンサータやストラテラが選択肢となります。これらの薬剤を処方するに先立って、当院では、心電図と採血を含めた身体的評価を行い、安全性を評価しています。
3. 青年期ADHD
青年期ADHDでもコンサータやストラテラは有効ですが、気分障害、不安障害、摂食障害を併存している場合は、まず、それらに対する治療を優先します。
ADHDを伴う症例の不眠や不安に対して、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬や睡眠薬が処方されていることがありますが、ADHDを伴う症例はベンゾジアゼピンへの依存を形成しやすいことが報告されており(Kousha et al.,2012)、当院の児童精神科外来では、原則として、これらの薬剤を処方していません。物質使用障害を併存している場合は、それらの専門的治療機関への紹介を行うことがあります。