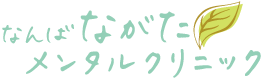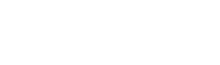摂食障害の成り立ち
生物学的な側面
米国を中心とする摂食障害の治療者・研究者の世界最大の組織である摂食障害アカデミーは、摂食障害を躁うつ病などと同様に生物的な基盤を有する重症な精神障害 (biologically based, serious mental illnesses: BBMI)ととらえています。背景には、民間企業が健康保険を担っている米国の医療事情があります。その結果、医療費が高くなりがちである摂食障害治療への風当たりは強く、どうしも、本当に病気なのだと強調する必要があるからです。
1. 遺伝的側面
欧米では10年ぐらい前から母子ともに摂食障害であることも稀ではなくなり、第2世代の時代に突入したと言われ始めました。日本では、幸いのことにそのようなケースはまだまだ稀です。欧米における家族研究(患者さんの親戚の方々に面接調査して摂食障害を有しているかどうか、摂食障害を有していない人の場合と比較する研究方法)では摂食障害患者の家族における摂食障害の有病率が有意に高く、双生児における一致率などから遺伝性を計算しますと50~83%でした。この数字を聞くと遺伝性の高い障害のように思われるかもしれませんが、躁うつ病などに比べますとずっと低い数字です。また、印象では、日本では患者さんの家族、親戚の方が摂食障害を有する率は、まだ高くないと思います。
分子生物学的な研究では、第1番、4番、10番染色体の領域と摂食障害との間に弱い連鎖が報告されています。また、摂食障害の危険因子と関連すると考えられるセロトニン、脳由来神経栄養因子(brain-derived neurotrophic factor: BDNF)、オピオイドなどの遺伝子との関連が指摘されていますが、これらの遺伝子の相関研究の結果は気分障害、不安障害、物質使用障害などでの結果と共通しています(これらの物質が脳内でどのような役割をしているのか、その説明は、また別の機会に)。
2. セロトニン仮説-強迫スペクトラム障害仮説
神経性無食欲症(拒食症)患者の脳脊髄液中のセロトニンの代謝物質は低下していて、体重が回復するとかえって上昇することが知られています。
また、後でもう一度述べますが、頑固に食すことを拒否し、低体重に固執する姿はまさに「強迫的」です。また病前から頑固であることから、病前性格の強迫性も記述されてきました。
それが、診断の信頼性を重視したアメリカ精神医学会の診断基準Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) が操作的診断基準の形式をとるようになると、強迫的性格から強迫性障害に軸足が移りました。DSM診断基準の各項目は、専門的で「文学的な」ではなく、より平易な言葉によって記述され、診断にはトレーニングが必要なものの、若い精神科医でも診断できるようになしました。また併存症として1人の患者に複数の診断をつけることができるようになりました。そこで、併存症研究が行われるようになると、摂食障害の患者では強迫性障害の併存が多いことが明らかにされました。また摂食障害に併存する強迫性障害の症状としては整理整頓にこだわることが多いことが報告されました。
このような強迫性障害の併存率の高さやセロトニン系との関連を通じて、強迫スペクトラム障害の1つに摂食障害を含めようとする動きがあります。しかし、強迫性障害には薬物療法が有効ですが、同じ薬剤の摂食障害への有効性は限定的です。そこで、確かに神経性無食欲症での強迫性障害の併存は対照群より多いものの、摂食障害の異質性(均質ではなく種々雑多なものの集団であること)を示しているに過ぎない、という意見になりつつあります。その結果、2013年に改訂されたDSM-5では、摂食障害は強迫スペクトラム障害に含まれませんでした。
3. その他の神経伝達物質などの関与
これまで視床下部-下垂体系、ノルアドレナリンやドーパミンといった神経伝達物質、各種の神経ペプチド、悪液質と関連する腫瘍壊死因子(TNF:Tumor Necrosis Factor)をはじめとするサイトカイン、脂肪細胞が分泌し強力な摂食抑制やエネルギー消費亢進をもたらすレプチンを初めとするアディポサイトカインなどが摂食障害の病因と関連するのではないかと期待されてきました。それらの物質やそのシステムは、確かに、摂食障害では対照群に比べ有意に上昇(または低下)しているのですが、どうしても単に低栄養状態や混乱した摂食行動の結末ではなくプライマリーなものだ(原因となる可能性のあるもの)とは証明し切れていません。また動物モデルによって摂食制限に続発する過食行動などを説明できますが、当然、身体像の歪みや自己誘発性嘔吐といった人間の本当の摂食障害の精神病理や行動は再現できません。大脳皮質などもっと上位の中枢神経系の関与が重要なのです。
4. 認知機能
摂食障害では実行機能(executive function、具体的にはセットシフトset shifting、環境の偶発的な変化・刺激に応じて反応を柔軟に変化させる能力)の困難さや、セントラル・コヒアレンス(central coherence)の障害(木を見て森を見ず、つまり細かい情報処理は得意だが、概観を見渡すことが苦手)が報告されております。また回復された神経性無食欲症 (拒食症) の患者や、摂食障害を有さない患者家族もセットシフトの困難さが認められるとの報告があります。しかし、この部分の研究は緒に就いたばかりで、これらがどれほど摂食障害の病理と関連するか、これからの研究を待たなければなりません。
摂食障害の成り立ち / B.心理社会学的な側面