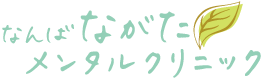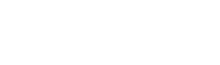社交不安障害(Social Anxiety Disorder、SAD)の 概念の成立と変遷
はじめに
2005年10月に日本で選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors、SSRI)が社交不安障害(Social Anxiety Disorder、以下SADと略す)への適応が認められてから、もう10年以上が経ちました。当初、日本の精神科医の間に、「正常範囲の性格」までに精神科診断を拡大し薬物療法の対象とする、アメリカ精神医学会の診断基準、治療指針に戸惑い、さらには反発もありました。しかし、その後の実地臨床での経験などから、その診断の重要、必要性が認められるようなり、以前のような反発は下火になったと思います。また、一般の人々の間にも、その名が知られるようになりました。しかし、精神科医以外の人にとって、身体疾患の診断と精神障害の診断が同じでないことは理解しにくい点だと思います。一般の方が、精神科の診断を身体疾患の診断と同様に考えてしまうのも当然です。それは、医療側の説明不足で、一般の方々の責任ではありません。本稿も、その理解を助けるために書かれていますが、まだまだ、難しいかもしれません。
まずは、恐怖と不安をどう考えるかの視点の整理が必要に思います。人間にとって、というより生物にとって恐怖は必要不可欠な機能です。わざわざ説明しなくとも分かっていることですが、大草原を歩むガゼル(ウシ科に属しますが外見は鹿です)がチータの気配を感じた瞬間、体全体が反応し、全速力で走り出すのは、生きていくために必須の要件です。また、予期することも重要です。山を登っている間、密林を歩いているときに、気温、湿度、風向、風速、雲の動き、変化から吹雪、嵐、雷来を感じ取り、それに向けた行動をとれることも生き延びるために重要です。
ところが、蜘蛛の姿、それがたとえ、無毒の微少な蜘蛛であっても、その姿を見かけたら、さらには以前に見たことのある場所であるだけで、恐怖し避けるために行けなった場合、それは恐怖症という診断をつけられます。また、ちょっとした自分の所作が、相手にどう感じられているのか、どう受け取られたのか、あり得ないことを考え、赤面し、腋下が汗にまみれ、ついには回避してしまうとき(このメカニズムについてどう解き明かすかいくつかのモデルを、認知行動療法、行動療法家が提案していますが)、その不安は過剰であると考えられます。
ですから、動物が、人類が森林の中で、もっと隠れるところのない草原のど真ん中で、生き延びるには、恐怖も予期も必須でした。ところが人の暮らし方は大きく変わっていきます。体に備わった機能が「進化」するより、人の暮らし方は加速度的に変化してゆきます。文明開化前では、群れて暮らすにしても、森林や大草原の中です、いくらでも一人になれました。ところが人類が農耕を始め集団で暮らすようになり(とくに水稲、水田という害虫、雑草との戦いが重要な、東アジア諸国では、労働集約が必要で密集して暮らしていました)、さらに現代の先進諸国では都市に密集して暮らすことになり、一人になることが難しくなると、人類は一人部屋を必要とするようになりました。そして、労働集約が必要なために密集して暮らした東アジアでは、「圧縮された近代化」(またどこかで説明します)の結果、「ひきこもり」が多発する結果となりました。
がん細胞はたった1つあっただけで「異常」ですが、人が恐怖を持つことは「正常」であり、「正常で健康な人」であっても、恐怖を有します。だから、精神障害の診断と、身体疾患の診断の有する意味は全く異なるのです。