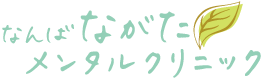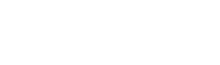摂食障害の成り立ち
心理社会学的な側面
多くの生物学的な指標がやせ(低栄養状態)や混乱した摂食行動の結末であることを否定しきれないなか、心理社会学的な側面の重要性は相変わらず無視できません。
1. 社会的な側面と病態の変化
摂食障害の臨床像、病態、精神病理の時代的変遷は、その背景にある社会・家族構造、価値観の歴史的変遷と無縁ではありません。宗教的な行為としてのやせや断食の歴史は長いです。多くの聖女が過酷な断食を行い、命を落としました。ですが、それは宗教行為であって病気・疾患ではなく、決して治療の対象ではありませんでした。ところが、ルネサンス、産業革命、市民社会の成立とともに聖人から医学モデル(sainthood to patienthood)へ、女性の地位向上と家族構造の変化、1950年代後半以降のツイッギー(Twiggy, 小枝,本名レスリー・ホーンビー、ミニスカートの女王と呼ばれたモデル)の登場の共に先進各国でダイエット文化の広がり、身体的欲求の抑制、禁欲主義、自己犠牲という断食から、現代的な美容のためのダイエットに移行し、摂食障害の広がりにつながります。
力動的には神経性無食欲症(拒食症・神経性食思不振症)は分離と自立の問題とされてきました。Hilde Bruch(1962)は①ボディイメージや身体の概念が妄想的な程度まで(delusional proportion)障害されており,②身体内部への感覚のとらえ方に障害があり、③思考、行動に全般に広がる無力感があり、自分のしたいことを全くしておらず、その場、その場で周囲の人に合わせて行動してだけと感じている、としました。その後Gerald Russell(1970)は、神経性食思不振症の中心的な精神病理が肥満に対する病的な恐怖であるとし、後年(1979年)には神経性大食症(神経性過食症)を提唱しました。そして現在、摂食障害の中心的な精神病理は身体像の障害とされています。具体的には、体重、体型、またはその両方の囚われていること、自己評価の決定において体型や体重が過剰に重きをなしていること、極度のやせ症状の深刻さを過少化または否認すること、自身の身体の捉え方に障害があること、例え低体重であっても体重増加に強烈な恐怖を感じることが、主要な症状とされています。
そして、西洋先進諸国とその他の国によって有病率に大きな差があることから文化結合症候群(culture-bound syndrome)の側面があります。しかし、国によって有病率に大きな差がある精神障害は摂食障害だけではありません。日本でも直接面接による有病率研究がなされるようになり、日米間で社交不安障害は8倍、双極性障害に至っては26倍の有病率の差があることが分かりましたが、それらを文化結合症候群という人はいません。
2. 併存症研究がもたらした種々のモデル
強迫スペクトラム障害との関連で既に紹介しましたとおり、病因についての想定を排除した(atheoretical)操作的診断基準の登場後、摂食障害における気分障害、不安障害、物質使用障害、パーソナリティ障害といった他の精神障害の併存率が高いことが報告され、それらの併存から病因を理解できるという気運がおこりました。その結果、気分スペクトラム障害、強迫スペクトラム障害、嗜癖モデル、境界性パーソナリティ障害などのモデルが提唱されました。しかし、それらの併存症の多くは摂食障害が改善すると軽減することから、半飢餓状態、過食と排出行為という混乱した摂食行動の結果である可能性を排除できません。性格やパーソナリティに関して、下坂幸三などが指摘した通り強迫性や統合失調性気質が注目されてきましたが、操作的診断基準の導入とともに強迫性パーソナリティ障害に注目が移り、一方で完全主義傾向や自己評価の低さなどが危険因子としてあげられています。ところが、最近では、これらは摂食障害の1群を説明することはあっても、全体を説明できるかには疑問が投げかけられています。
摂食障害の成り立ち / C. 治療的観点から